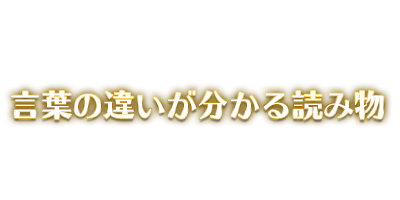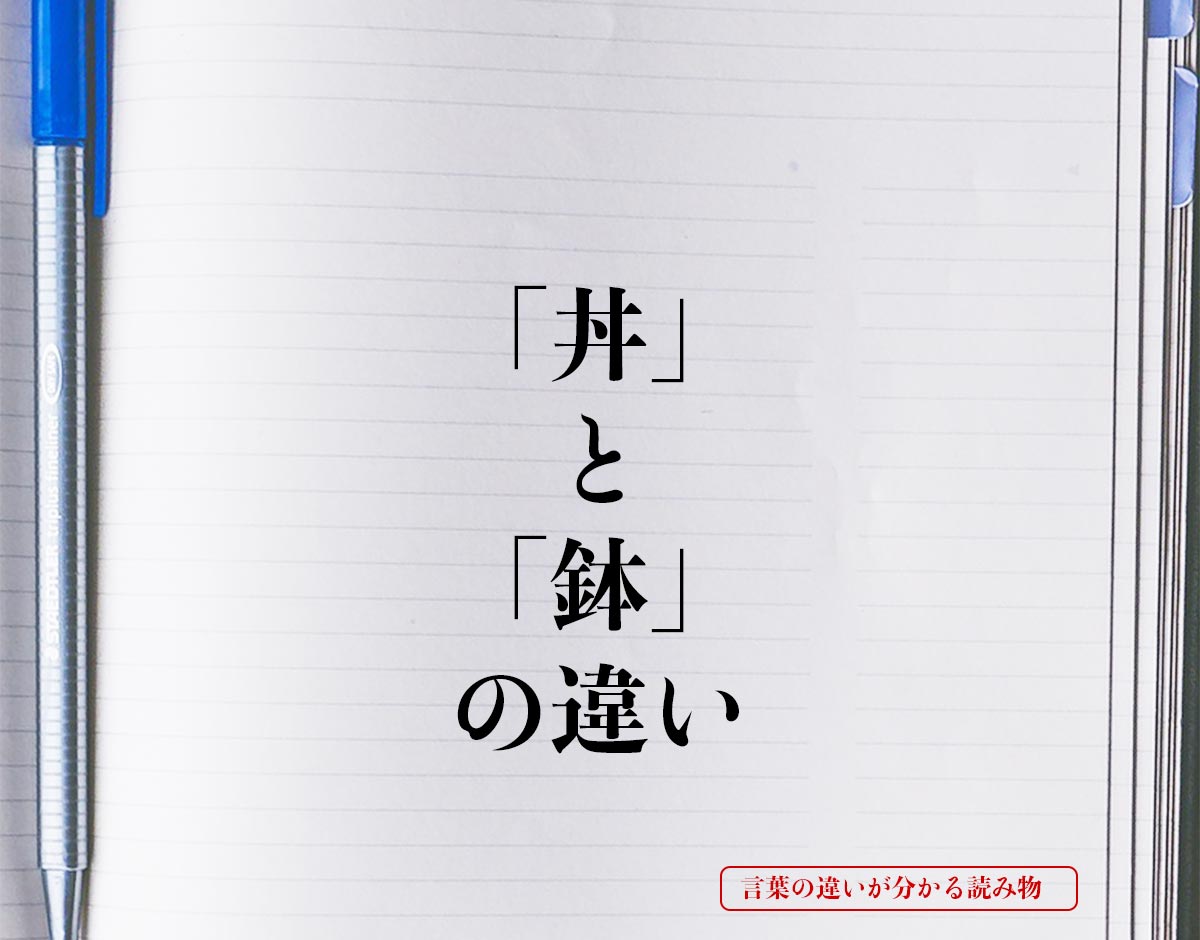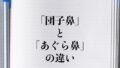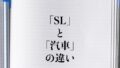この記事では、「丼」と「鉢」の意味や違いを分かりやすく説明していきます。
「丼」とは?
陶磁器製で厚みがあり、深い鉢を「丼」【どんぶり】といいます。
工場で作られたものから、職人の感覚が表れた形、柄の高級な「丼」も人気がある器です。
球体を真ん中で半分に切った半球型の器でもあり、深さがあるので汁料理やご飯をよそい、上におかずをのせた丼物を作ったとき使います。
元々は江戸時代にケチな店主が1杯だけしか料理を出さないところが「慳貪屋」【けんどんや】と呼び、単品で出す「丼」につながるのです。
「鉢」とは?
お茶碗よりも大きく、口が広めに作られている食器を「鉢」【はち】といいます。
副菜を盛るのにちょうどいい大きさと深さの「小鉢」や、汁をたっぷり入れて使うのに重宝する「深鉢」が揃い、料理に応じて使い分けられている食器です。
素材は陶磁や石、木製と色々あり、料理の温度に適した「鉢」を選びます。
また、色や柄も豊富で、食材を華やかに見せるために内側が赤色であったり、葉物をお浸しにした料理には黄色や白が映えるため選ばれているのです。
「丼」と「鉢」の違い
ここでは「丼」と「鉢」の違いを、分かりやすく解説します。
麺を入れて汁をたっぷり入れるとき選ぶ「丼」は半球型の食器を指します。
「丼」には熱い料理を入れるのに適した陶磁器製だけではなく、軽くて片手で持ちやすい漆器製も揃うのが魅力です。
また、とんかつをダシのきいた汁に染み込ませて、玉葱を入れて溶き卵をかけて煮た「かつ丼」や、海の幸が色々と酢飯の上にのった海鮮丼など色々な食材から作った料理を指します。
もう一方の「鉢」は弥生時代に甕【かめ】として使われていた土器からきている食器です。
浅鉢や深鉢といったものがあり、料理の汁気の量により使い分けられています。
まとめ
半球型の食器を指しますが、使い方に違いが見られます。
どういった料理で使われているか、大きさや深さに目を向けてみるといいでしょう。