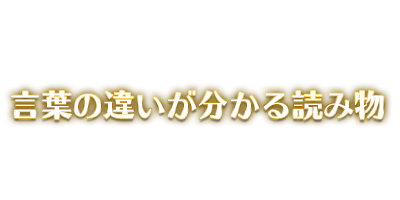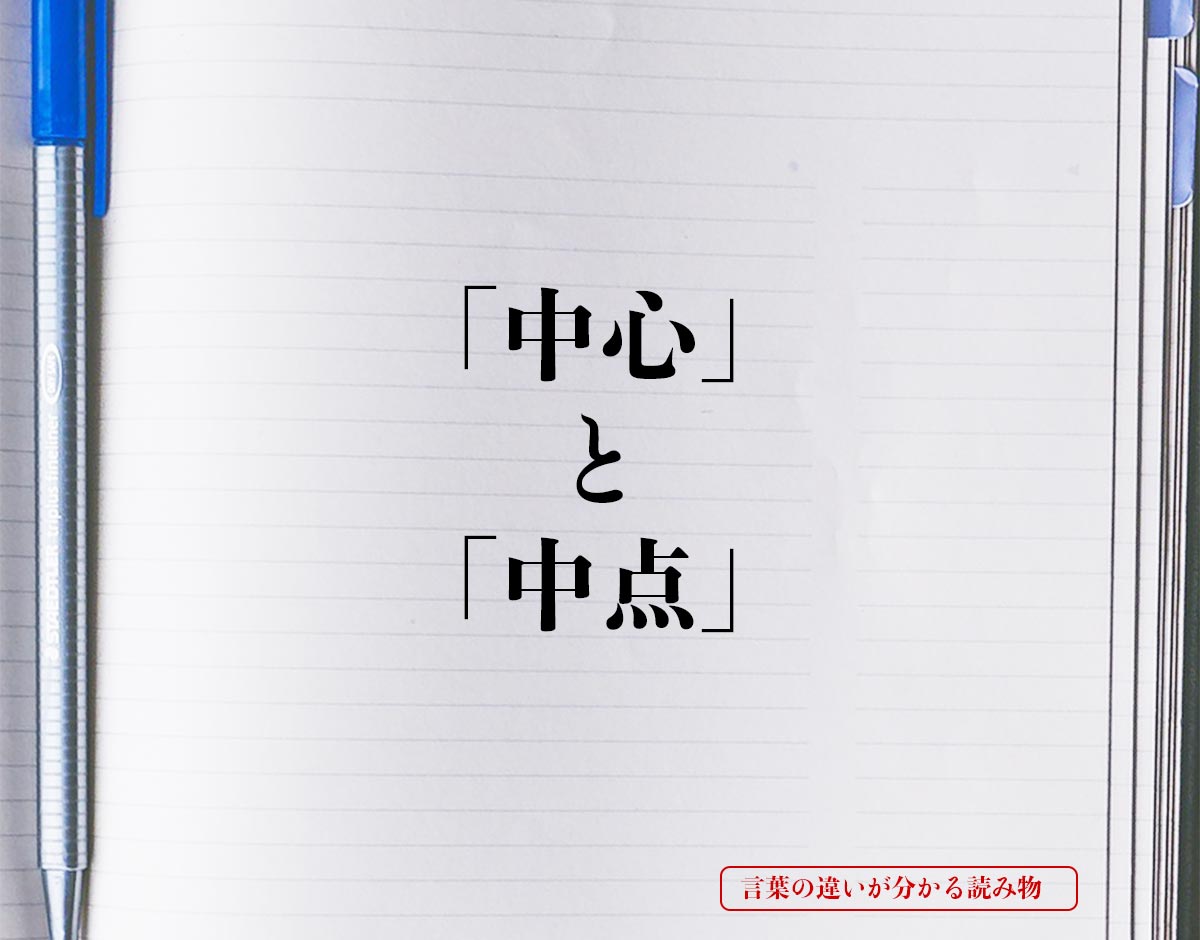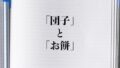数学を学んでいると、見分けが難しい言葉が出てくることもあります。
この記事では、「中心」と「中点」の違いを分かりやすく説明していきます。
正しい意味を知って、楽しく学んでいきましょう。
「中心」とは?
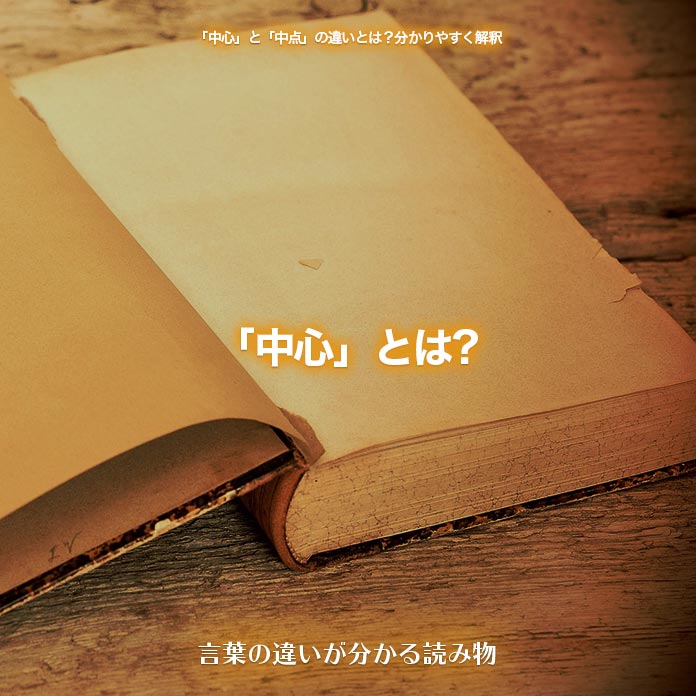
中心(ちゅうしん)とは、図形の真ん中のこと。
その図形の、センターにあたる点です。
おもに「円の1番真ん中の点」を中心と呼んでいます。
図形のおへそに当たる部分です。
目の前に、ある大きな円があったとします。
この円の中心から、円周までの長さはどこを取っても「同じ長さ」です。
つまり右上から進んでも、左下から進んでも、どの場所を通っても同じ距離ですすめます。
円周からの距離が等しい場所、いくつもの線が交差する点が「中心」です。
中心は数学でつかう難しい言葉に思えますが、実生活でもよく出てくる言葉です。
たとえばクリスマスケーキをホールで買ってきたとき。
ケーキの中心が分かれば、家族みんなで同じ大きさのケーキを切り分けられます。
不公平を無くしたいとき、大活躍してくれるものが「中心」です。
「中点」とは?
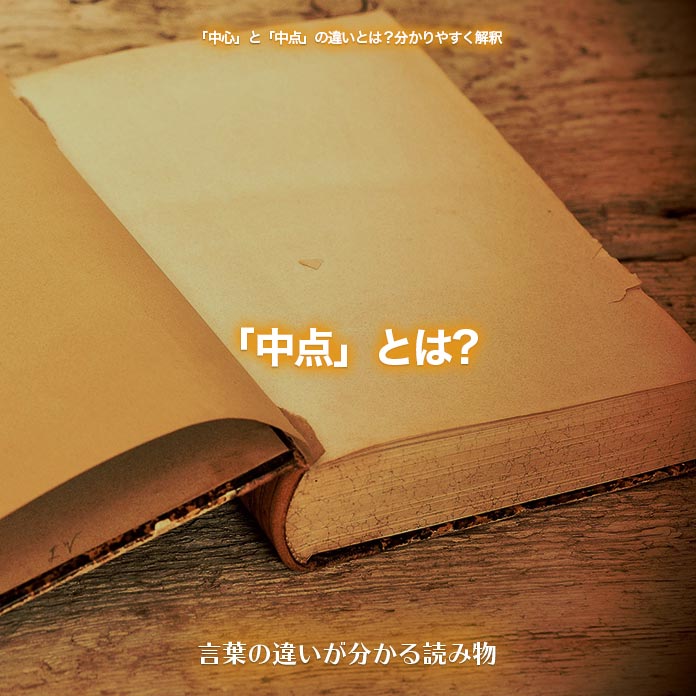
中点(ちゅうてん)とは、線の真ん中のこと。
その線の、センターを意味する点です。
ひとつの線を等しく2つに分けたいとき、重要な意味をもつ点です。
たとえば目の前に、長い道があったとします。
向こう側に友達がいたとき、ちょうど真ん中で落ち合いたいと思ったとします。
こちらから進んでも、向こうにいる友達が進んでも、不公平にならない点が「中点」です。
中点に立つと、両端までの長さは常に同じ。
どちらの端に向かっても、同じ距離で進んでいけます。
中点は古代ギリシャ時代に生まれた、幾何学の考え方です。
現代の生活でも、欠かせないものとなっています。
例えば鉄道の駅を決めるとき。
隣の駅と隣の駅のちょうど中間(中点)に駅があると、そのエリアに住んでいる人にとって快適な駅になります。
ひとつの距離や線を等しく分けたいとき、使えるアイデアが「中点」です。
「中心」と「中点」の違い
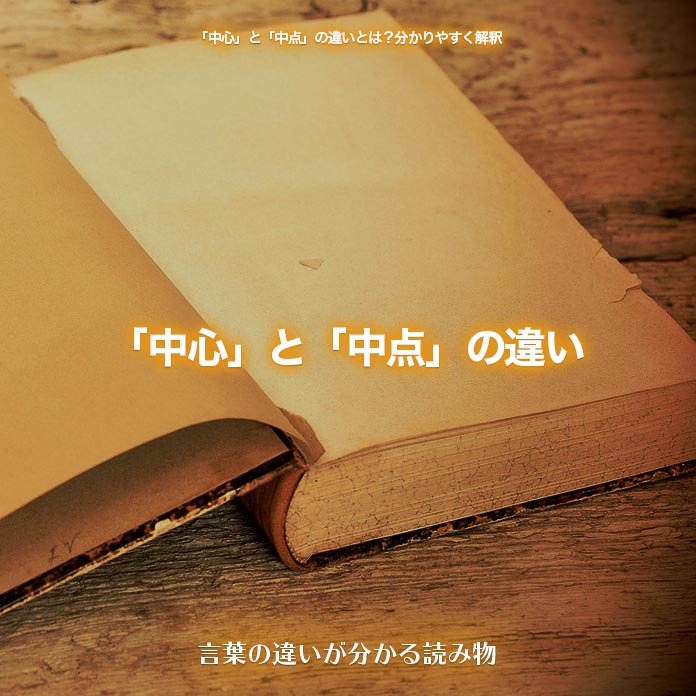
どちらも数学の用語ですが、難しく感じられます。
「中心」と「中点」の違いを、分かりやすく解説します。
・中心はO、中点はM
中心はおもに円などの図形の、センターの点をあらわします。
また中点は直線の、センターの点のことです。
図形の真ん中の点が「中心」。
そして線の真ん中の点が「中点」になります。
原点のことをラテン語で「origin」というので、中心のことを「O」としめします。
また中点は英語で「middle point」というので、中点のことは「M」といいます。
Oが中心なら、Mが中点です。
どちらもテストでよく問われる語なので、覚えておくと便利です。
まとめ
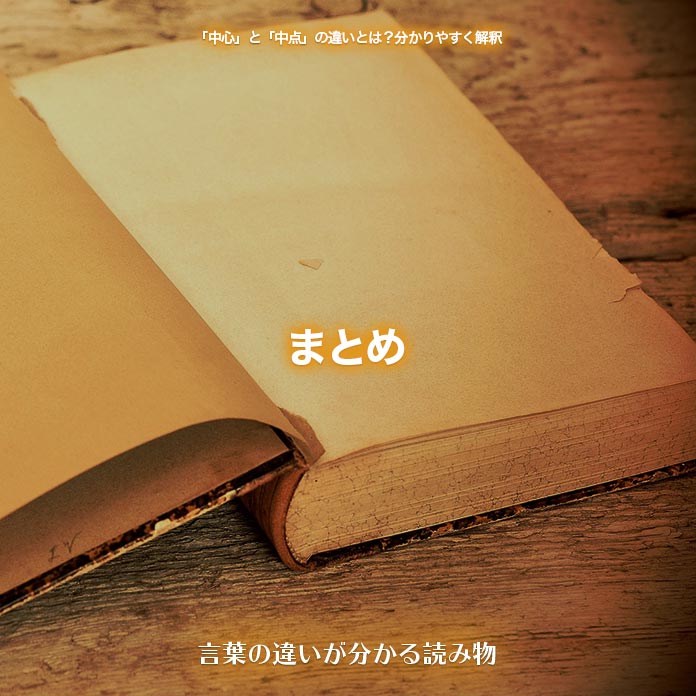
「中心」と「中点」の違いを分かりやすくお伝えしました。
中心は円などの図形の、おへその部分のこと。
真ん中の点をあらわします。
中心から円周までの長さは、どこを取っても等しくなります。
そして中点は、直線の真ん中の点です。
中点から両端までの長さは等しくなります。
数学の専門用語を正しく知って、知識をボリュームアップさせていきましょう。