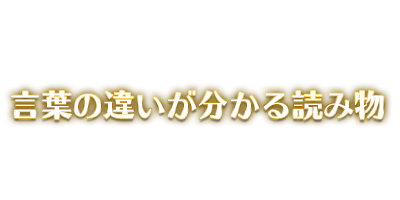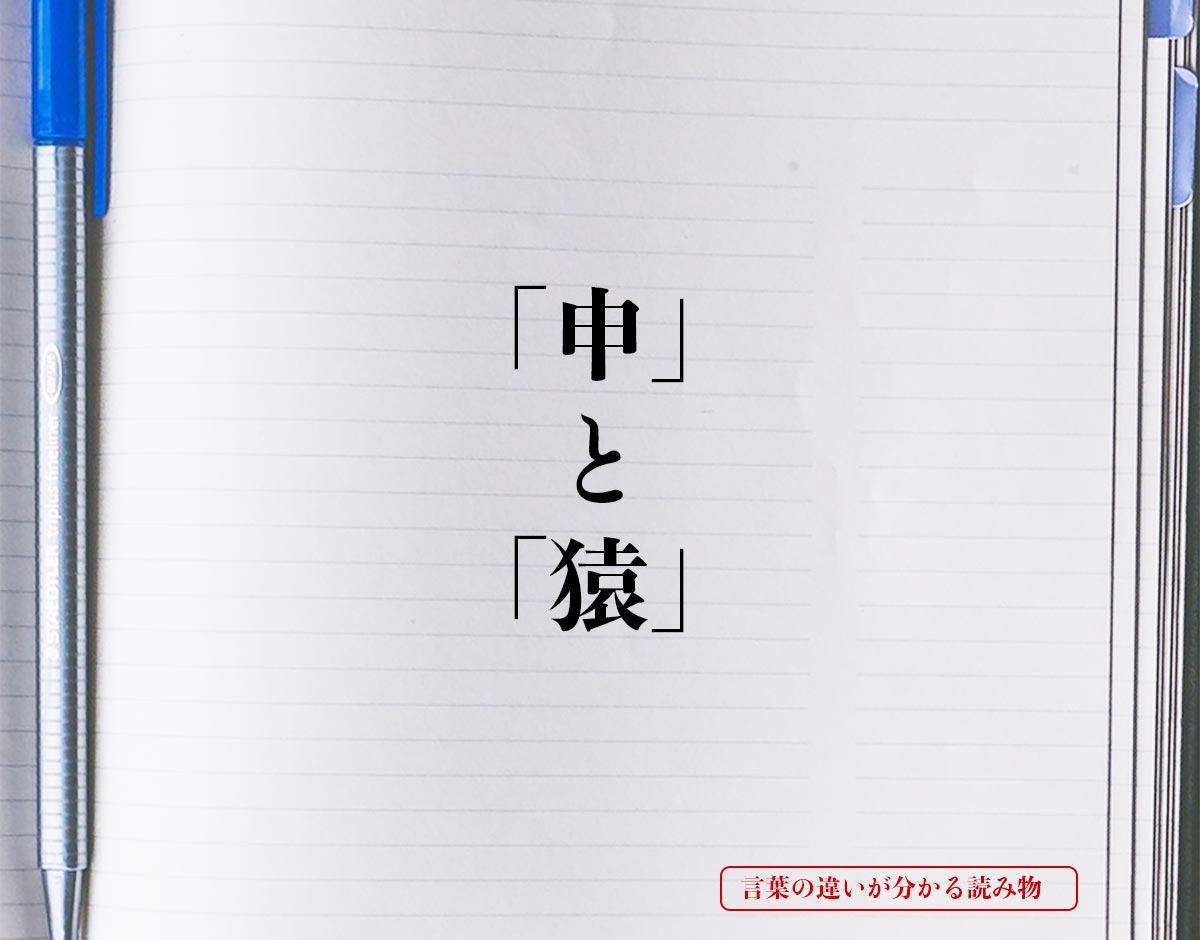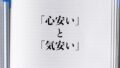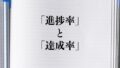皆さんは「申」と「猿」にどのような意味があるかご存知でしょうか?
そこでこの記事では、「申」と「猿」の違いを分かりやすく説明していきます。
「申」とは?
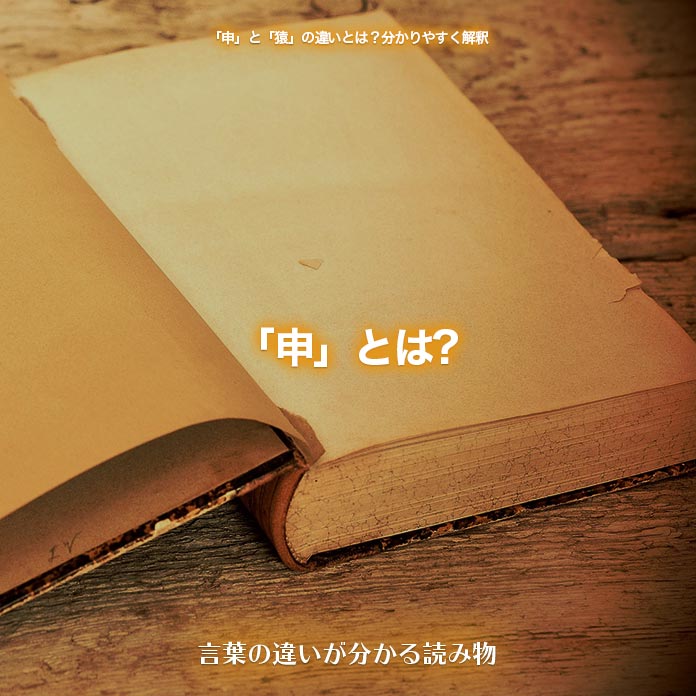
「申は「さる」と読みますが、この「申」が「十二支の1つで第7」に当たります、「方角で西南西・時刻で午後四時、あるいは15時~17時までの間を指しているもの」です。
「猿」とは?
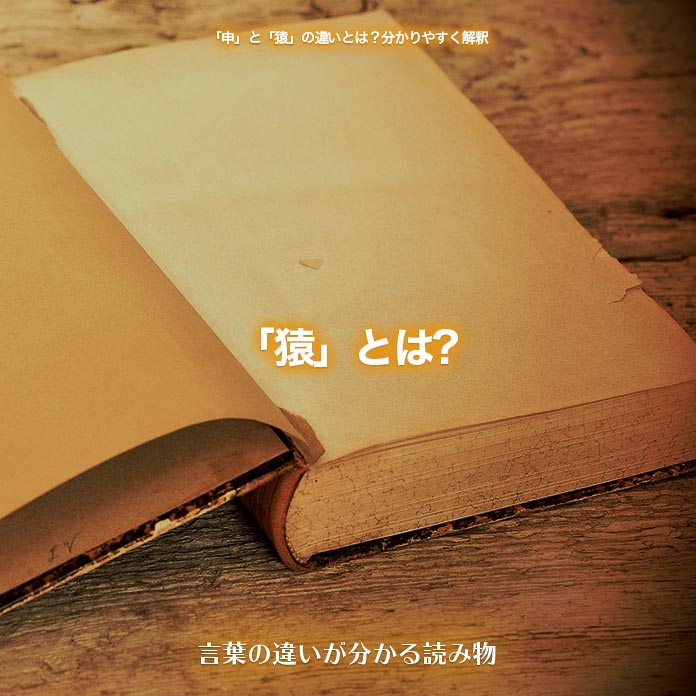
「猿」も同じく「さる」という読み方になるのですが、「形が人によく似ている猿猴類の動物の総称」を指しています。
木登りが得意で知能も発達している点が特徴的な生き物でもあります。
「申」と「猿」の違い
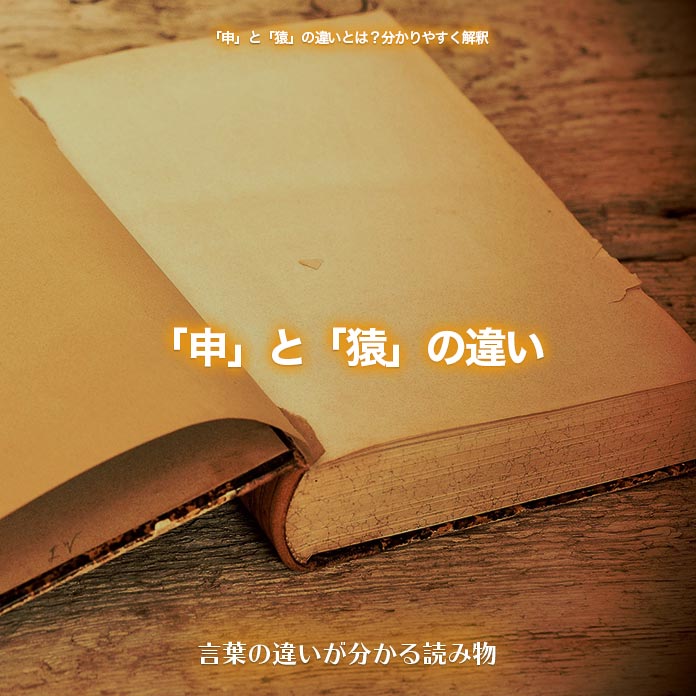
では、「申」と「猿」にどのような違いがあるかを見ていきましょう。
私たちが一般的に霊長類の中で意味する動物の場合は、「猿」となります。
一方の「申」は干支の1つであるものの、本来「さる」という意味がなったのです。
しかし、十二支が動物と結びつけられて考えられるようになってから、「申」の年は「さる」の年とされるようになった経緯があります。
尚、「申」は甲骨文字でも表されており、稲妻をイメージしたものと言われています。
雷が雨とともに起こることから「申」の上に「雨」がついて「電」の字が形成されたともされているのです。
この「申」は十二支で7番目に当たり、中国では月で言うと7月を意味しています。
日本でも、7月は積乱雲が発達して雷と伴う雨が降る季節ですが、このことからも7月が申に当たることが理解できるかもしれません。
「申」の例文
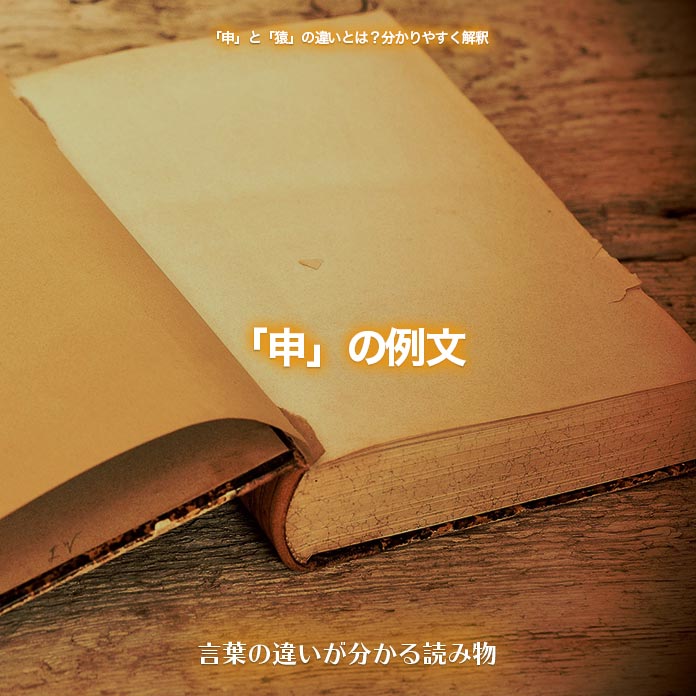
では、ここで「申」の例文を見てみましょう。
どのような文章があるでしょうか?
・『俺さっき調べてみたんだけど、歴史上の人物の中で申年って、豊臣秀吉がいたんだよな。俺が底辺から這い上がってここまでの地位を築き上げることができたのも、同じ申年ってことが関係していないかな?』
・『申年の人の性格って、適応力が高くて多くの人たちに親しまれやすいんだって。僕も申年だからそんな性格だと感じていたけど、本当にそうなんだな。 まさに天性だって自信を持っちゃった』
「猿」の例文 次に「猿」の例文を見ていきましょう。 具体的には以下のようなものが挙げられます。 ・『最近、ウチの近所に猿が出て来たんだ。山から下りてきたんだけど、山に食べるものが少なくなってきたのかもしれないな。たぬきや鹿にも畑を荒らされて困っているのに、ますます頭が痛くなってきたよ。これからどうしよう?』 ・『お前って、マジで猿顔だよな。笑っちゃいけないと思いながら、どうして噴出してしまうんだ。仕草もそのままだし。もしかして親戚にお猿さんがいたりして』 まとめ
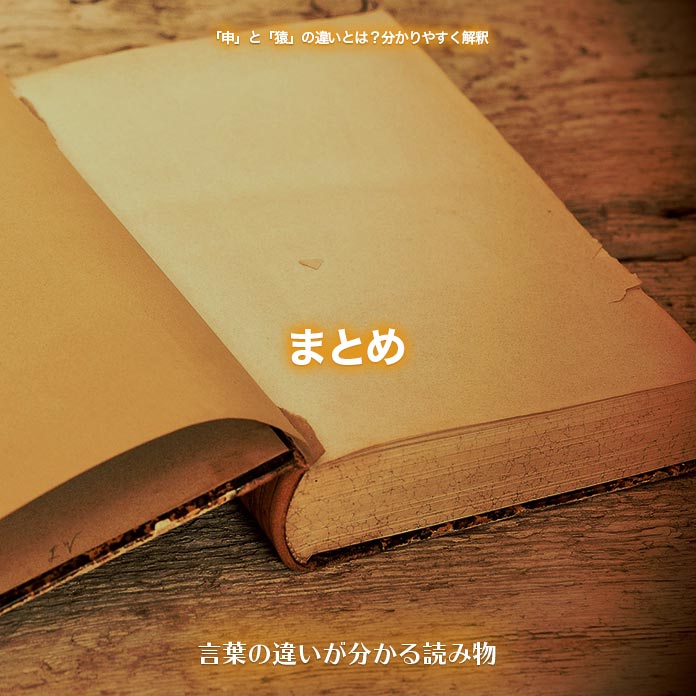
ここまで「申」と「猿」の意味や違いを説明してきました。
日常会話の中で「申」を使うことはあまりないかもしれませんが、「猿」は身近な存在として親しまれています。
同じ「さる」ですが、個々の意味を理解することで、言葉の雑学として言葉に親しむこともいいのではないでしょうか。