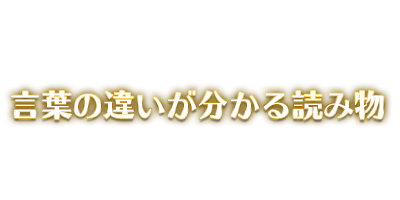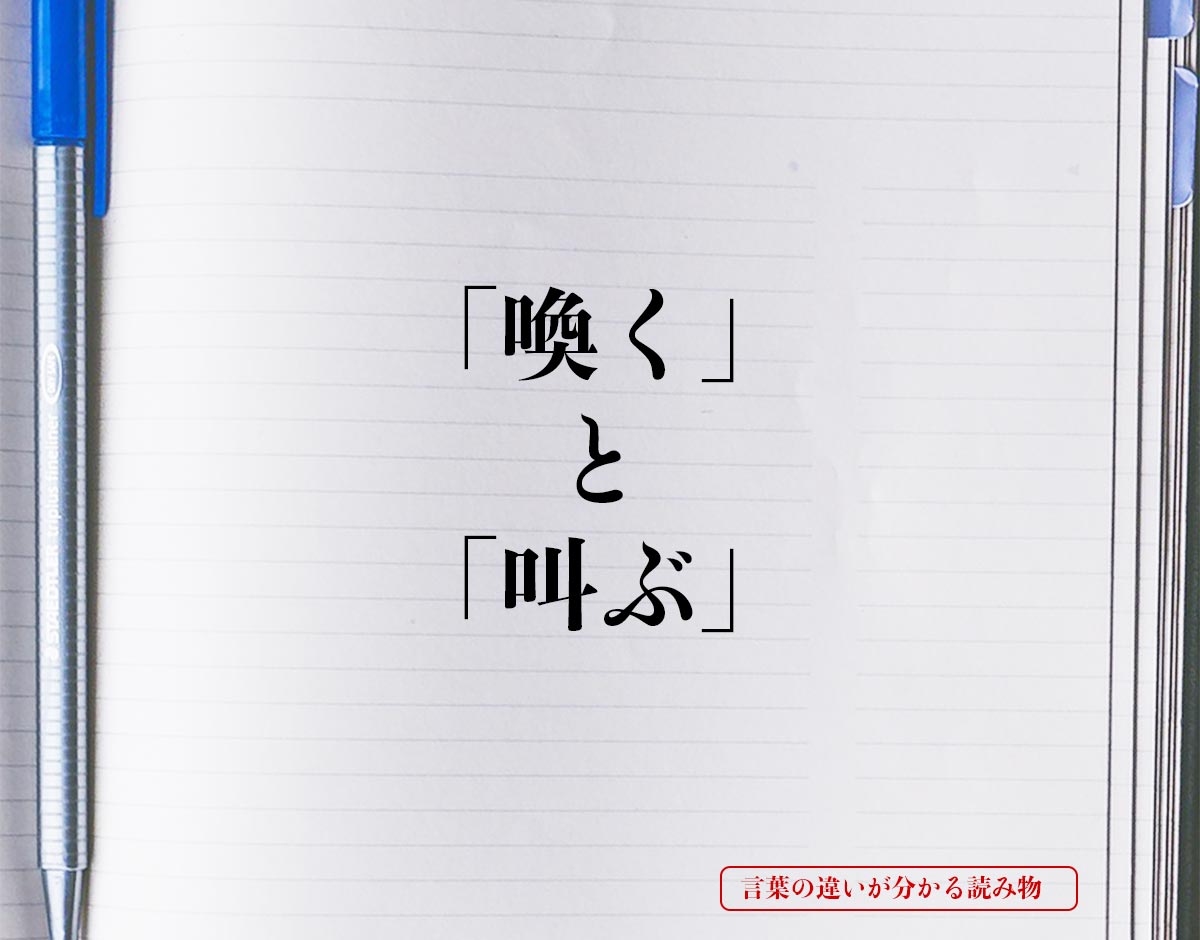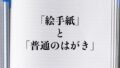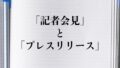この記事では、「喚く」と「叫ぶ」の違いを分かりやすく説明していきます。
「喚く」とは?
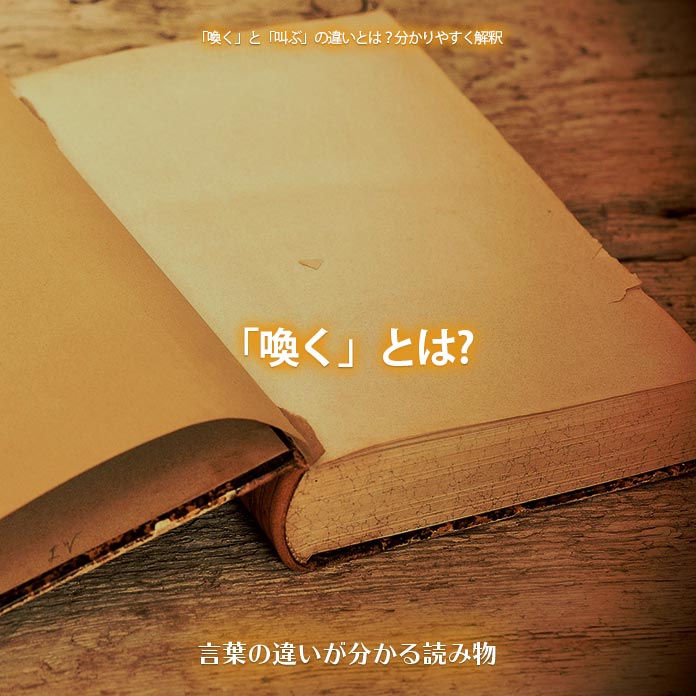
大声を出すこと、大声を出してやかましくすることです。
不平不満や訴えなどを表すための行為をいいます。
たとえば、おもちゃ売り場でこの行為をしている子どもを見かけることがあります。
おもちゃ売り場に欲しいものがありました。
子どもは買ってと親にお願いをします。
しかし、親はダメだといいます。
それでも子どもは諦めることができず、何度も買って買ってといいます。
しかし、しつこくお願いをしても親はいいと言ってくれません。
次第に子どもの声が大きくなり、やかましくなってきました。
この場合は、おもちゃを買って欲しいという訴えを表すために、この行為を行っています。
注射をされるときに、この行為をする子どももいます。
注射は痛くて嫌です。
嫌なものを避けたいために、わーなど大きな声を出すことがあります。
声が大きくてやかましいです。
この場合は、注射を受けたくないという訴えを表すためにこの行為をしています。
「喚く」の使い方
大きな声を出していて、それが不平不満や訴えなどを表したい場合について使用をします。
遠くの人を呼ぶために大きな声を出すことには使用しません。
「叫ぶ」とは?
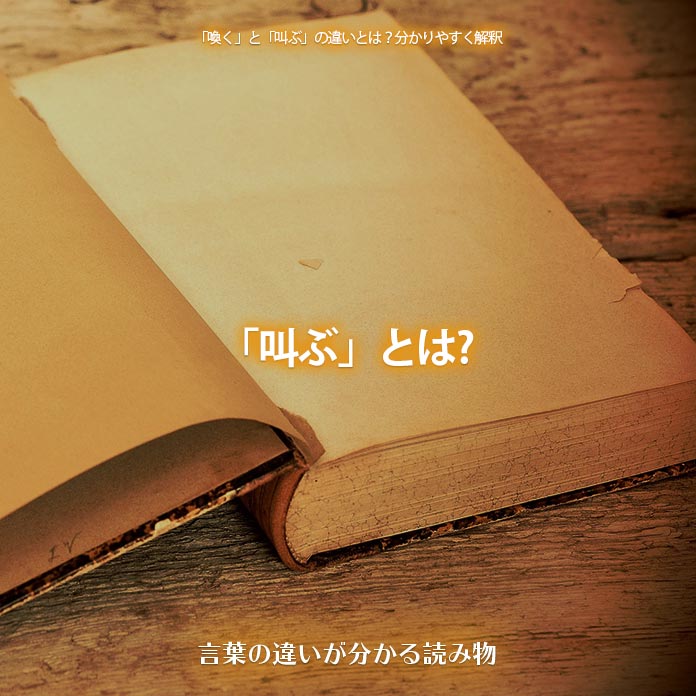
「叫ぶ」には2つの意味があります。
ひとつは、大きな声を出すです。
遠くに声が届くようにするためや、驚いたり恐怖を感じたりしたためにこの行為が行われます。
たとえば、道路の向こう側に知り合いがいたとします。
この人に話したいことがあるので呼び止めたいです。
道路をすぐには渡ることができず、このままでは知り合いが遠くに歩き去ってしまいます。
そこで、「おーい、○○さん」と大きな声を出しました。
この行為を指します。
また、ジェットコースターに乗ったり、お化け屋敷に入ったりしたときにも、この行為がされることがあります。
キャーといった大きな声が地上にまで聞こえてきます。
これは、驚いたり恐怖を感じたりしたために起こっています。
もう一つの意味は、世の中に対して強く言い知らせるです。
「原発廃止を叫ぶ」といった使い方をします。
「叫ぶ」の使い方
大きな声を出すという意味で使われることが多いです。
「喚く」と「叫ぶ」の違い
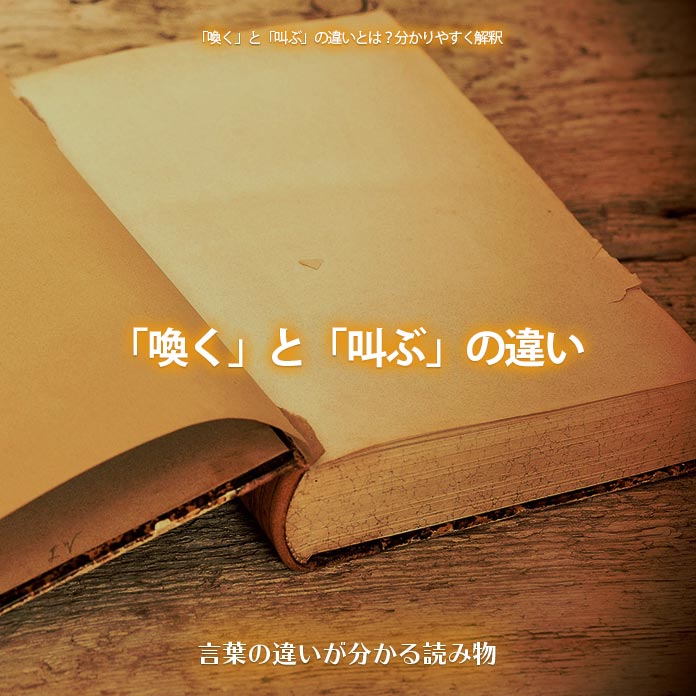
大きな声を出すという意味が似ていますが、どうして大きな声を出すのかという点に違いがあります。
前者は、不平不満や訴えなどを表すためです。
後者は、驚いたり、遠くに声を届けたりするためです。
また、世の中にいい知らせるという意味もあります。
「喚く」の例文
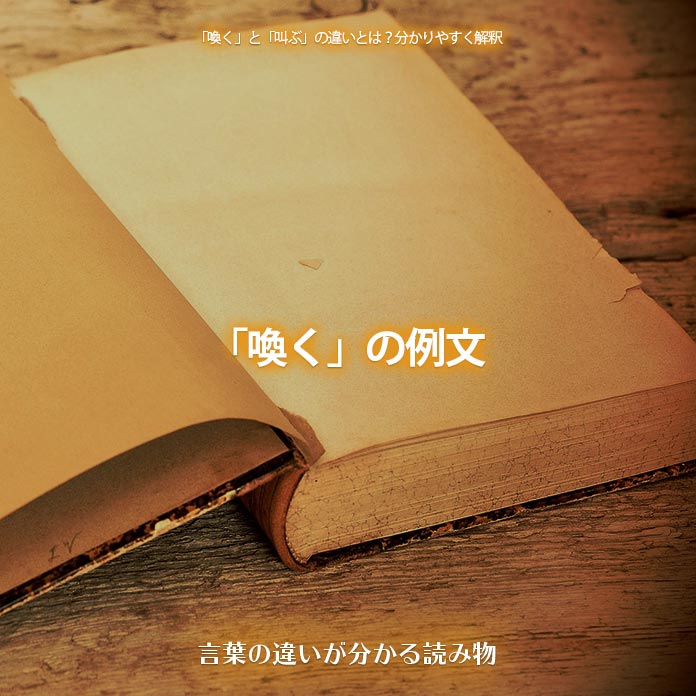
・『喚く声がうるさい』
・『喚くけれど気にしない』
・『繰り返し喚く』
・『ひどい言葉で喚く』
「叫ぶ」の例文
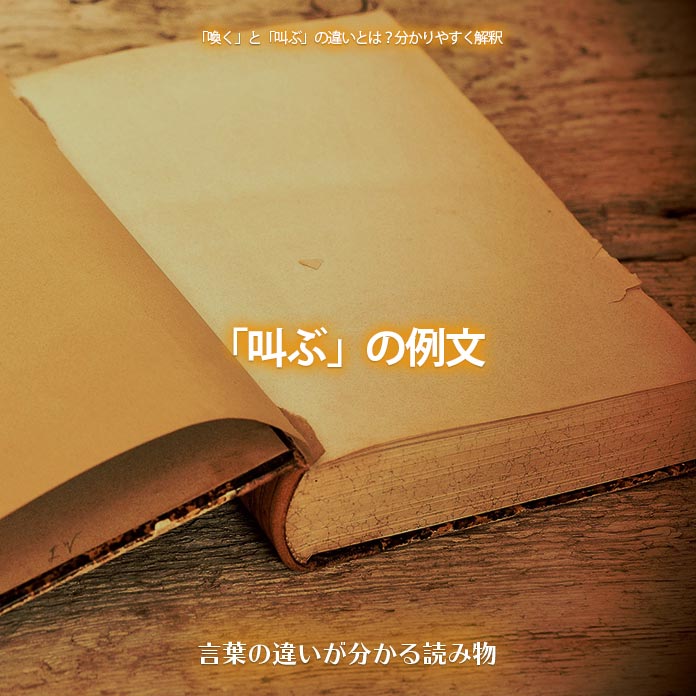
・『ジェットコースターに乗って叫ぶ』
・『叫ぶ声が聞こえた』
・『知らない言葉を叫ぶ』
・『感謝を叫ぶ』
まとめ
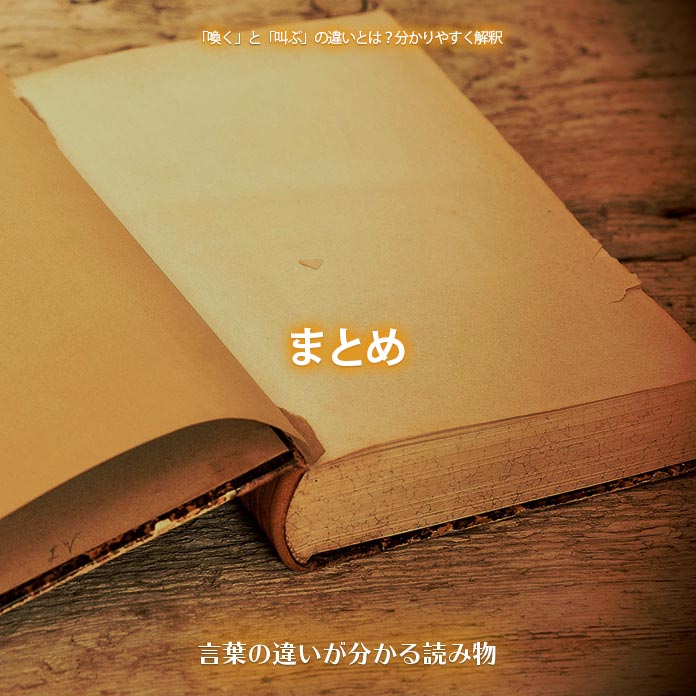
大きな声を出すという意味が似ていますが、それをするのはなぜなのかという点に違いがあります。