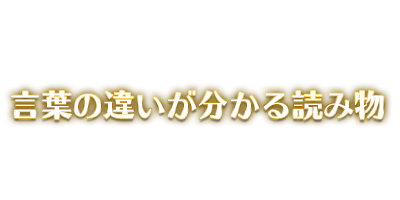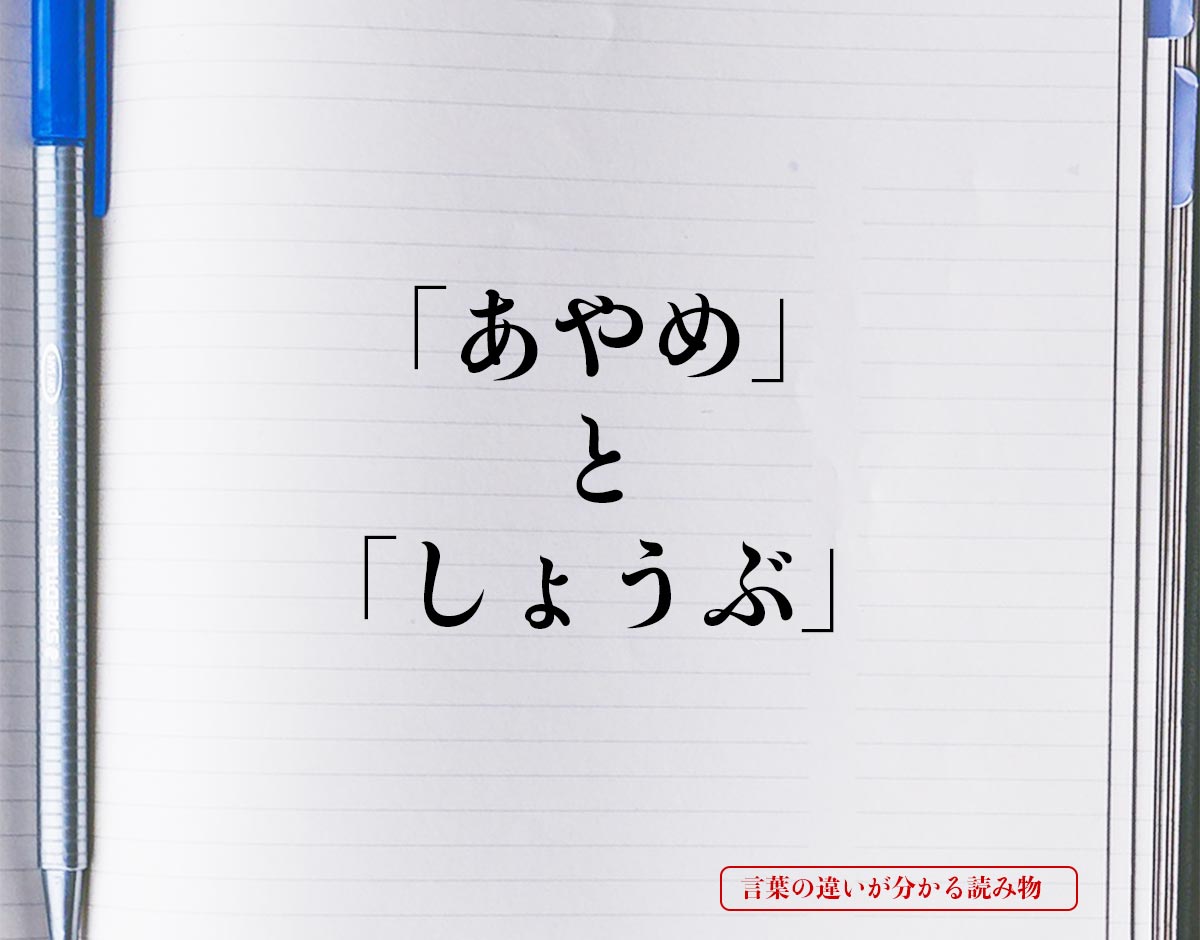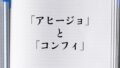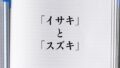この記事では、「あやめ」と「しょうぶ」の違いを分かりやすく説明していきます。
「あやめ」とは?
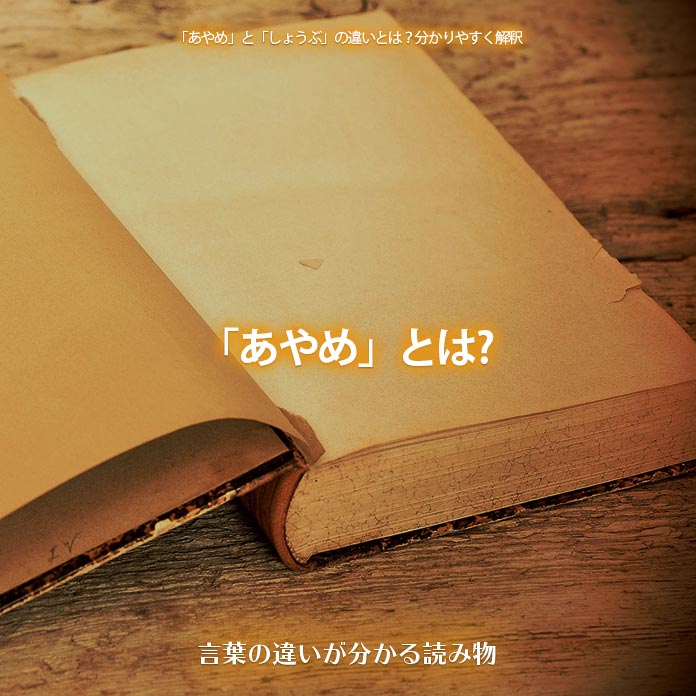
「あやめ」とは、アヤメ科の多年草の植物です。
葉は細長く、初夏に紫や白色の花が咲きます。
花びらは網目の模様があります。
同じアヤメ科の花菖蒲(はなしょうぶ)に似ています。
「あやめ」を使った例文をいくつかご紹介します。
『「六日のあやめ、十日の菊」は、時期に遅れて役に立たないことを表すことわざです』、『あやめの節句は5月の節句のことを言います』、『ゴールデンウィークの連休中にあやめの花を見に行く予定です』「あやめ」を漢字で書くと、「菖蒲」、「綾目」、あるいは「文目」となります。
「しょうぶ」とは?
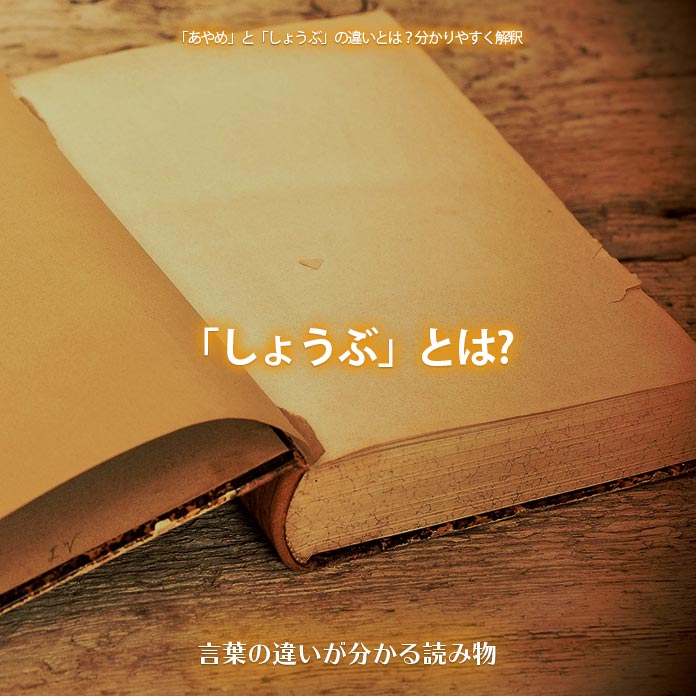
「しょうぶ」とは、サトイモ科の常緑多年草の水場に生える植物です。
葉も花も細長いのが特徴です。
花は薄緑色です。
また、「しょうぶ」はアヤメ科の「花菖蒲」の通称でもありますが、この2つは別の植物です。
「しょうぶ」は漢字では「菖蒲」と書きます。
「しょうぶ」を用いた例文をいくつか挙げてみます。
『5月5日の端午の節句に、しょうぶ(菖蒲)を湯船に浮かべたしょうぶ(菖蒲)湯に入る習慣があります』、『今度の休みにしょうぶ(菖蒲)園へ、しょうぶ(菖蒲)を見に行きたいと思っています』、『この公園はしょうぶ(菖蒲)で有名な観光スポットです』
「あやめ」と「しょうぶ」の違い
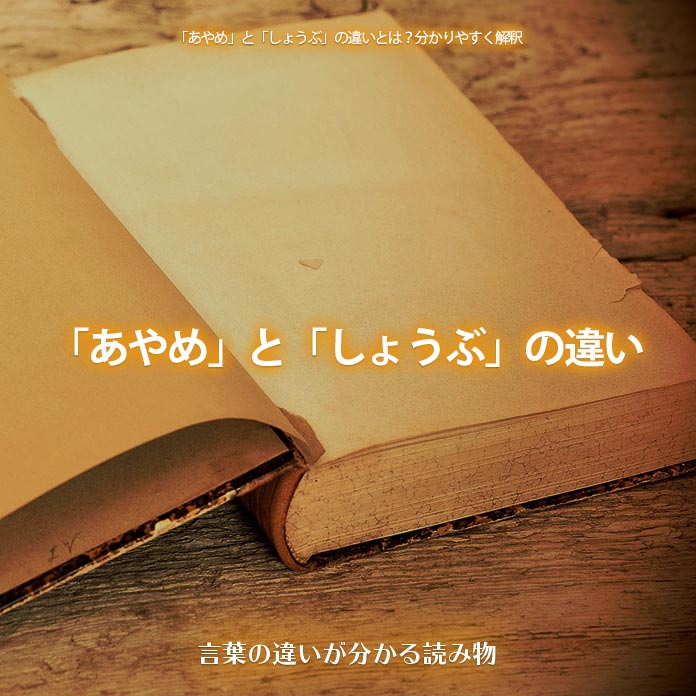
「あやめ」と「しょうぶ」の違いを、分かりやすく解説します。
「あやめ」とは、アヤメ科の多年草の植物で、紫や白い花をつけます。
一方、「しょうぶ」はサトイモ科の常緑多年草の水場に生える植物で、細長くて薄緑色の花が咲きます。
「あやめ」と「しょうぶ」は分類も違いますし、花の形も違っています。
また、「花菖蒲」はアヤメ科なので、「しょうぶ」の通称として知られていますが、「しょうぶ」と「花菖蒲」は別の植物です。
さらに、「あやめ」は5月上旬頃に花が咲きますが、「花菖蒲」は5月下旬から6月に開花するので、この点も異なっています。
まとめ
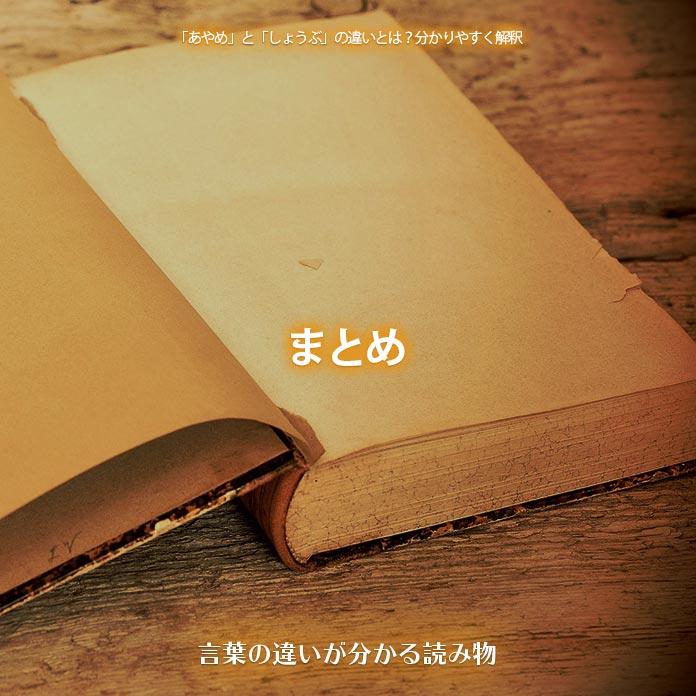
「あやめ」と「しょうぶ」が似ていて分かりにくい理由は、「しょうぶ」が「花菖蒲」だと捉えているからかもしれません。
確かに「あやめ」も「花菖蒲」もアヤメ科の植物なので、見た目にも共通点があると言えます。
ですが、「しょうぶ」はサトイモ科の植物で、花の見た目がまったく違います。
なので、このことを知っていれば、「あやめ」と「しょうぶ」を見分けやすくなるでしょう。
もともと、「しょうぶ」も「あやめ」と呼ばれていました。
なので、「あやめ」と「しょうぶ」の区別が分かりにくいと感じるのも、このような名前のルーツがあったからで、当然のことかもしれません。
これらの違いを知ったことで、これからは「あやめ」や「花菖蒲」の花の鑑賞だけではなく、「しょうぶ」の花も観察してみるのも良いでしょう。
「しょうぶ」の花は「あやめ」や「花菖蒲」に比べると地味で目立ちません。
ですが、そこに「しょうぶ」の素朴な花の良さを発見できるかもしれません。