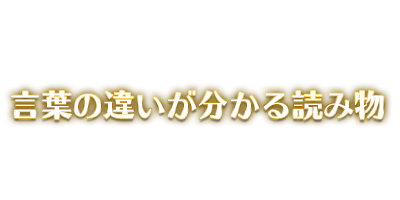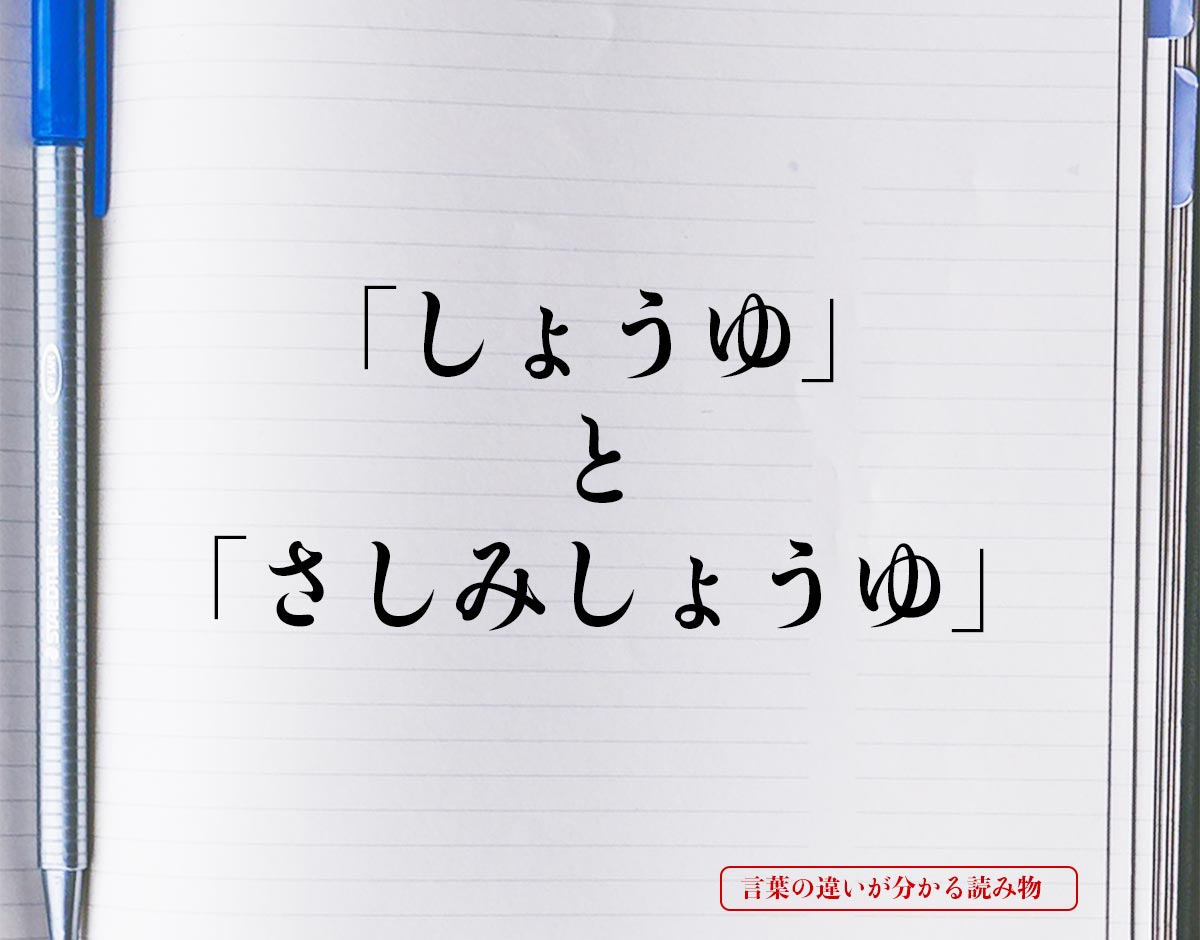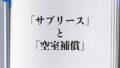この記事では、「しょうゆ」と「さしみしょうゆ」の違いを分かりやすく説明していきます。
この2つの言葉には、どのような意味と違いがあるでしょうか。
「しょうゆ」とは?
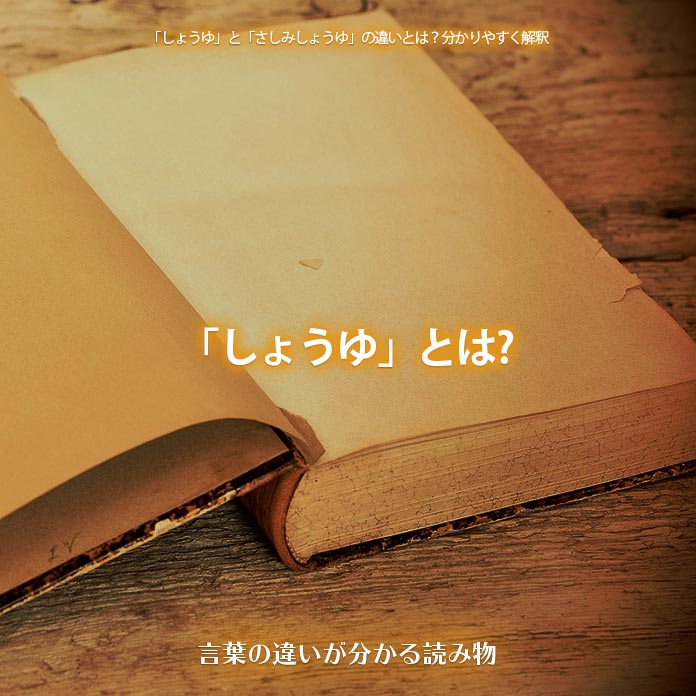
「しょうゆ」という言葉には、どのような意味があるでしょうか。
「しょうゆ」は、「醤油」と漢字表記します。
「しょうゆ」は、「日本独特の調味料の一つ。
小麦や大豆を原料とした麹に、食塩水を加えて、発酵させたあとで、絞った液体のこと」という意味があります。
「しょうゆ」には、様々な種類があり、「濃い口しょうゆ」や、「薄口しょうゆ」、「たまりしょうゆ」などがあります。
日本全国で「しょうゆ」は作られていて、地域によって味の違いがあるため、マニアも存在します。
このような様子を、「地方のしょうゆを買い求め、ソムリエをするしょうゆマニアがいる」という文章にできます。
また、血圧が高い人は、塩分の多い「しょうゆ」を控える必要があるかもしれません。
この場合は、「血圧高めなので、減塩されたしょうゆを使うことにする」などという文章を作ることができます。
「さしみしょうゆ」とは?
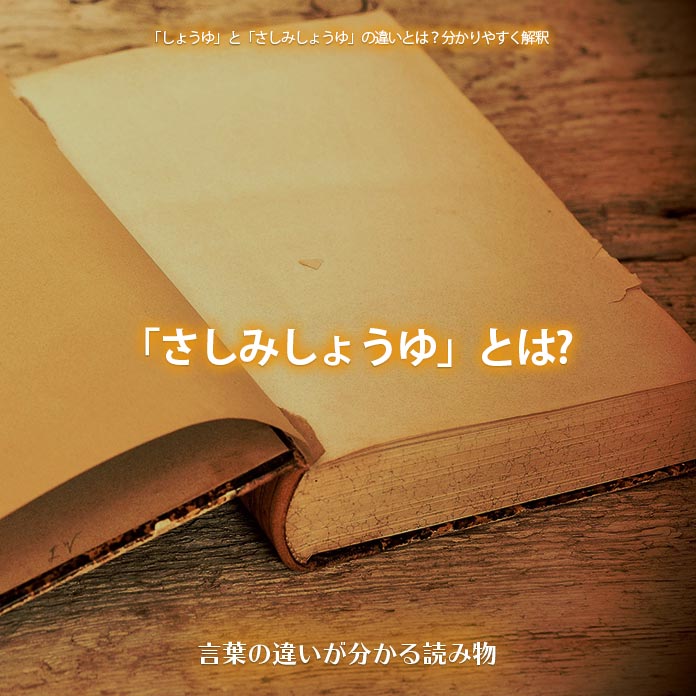
「さしみしょうゆ」という言葉には、どのような意味があるでしょうか。
「さしみしょうゆ」は「刺身醤油」と漢字表記します。
「さしみしょうゆ」は、「刺身を食べるためのしょうゆ」という意味があります。
一般的な「しょうゆ」は、料理の味付けをするために使うことを前提としているため、そのまま口に入れると、苦みが強い場合があります。
そこで、刺身を美味しく食べるために、適切な味に調えたのが「さしみしょうゆ」になります。
風味や味などが濃厚である一方で、苦みなどが抑えられています。
出汁や魚介類エキスなどが加えられていて、うま味が足されているものもあります。
刺身を購入したときに、しょうゆを選ぶときは、「さしみしょうゆ」を選ぶ場合、「刺身を食べるなら、さしみしょうゆ一択だ」などという文章を作ることができます。
「しょうゆ」と「さしみしょうゆ」の違い
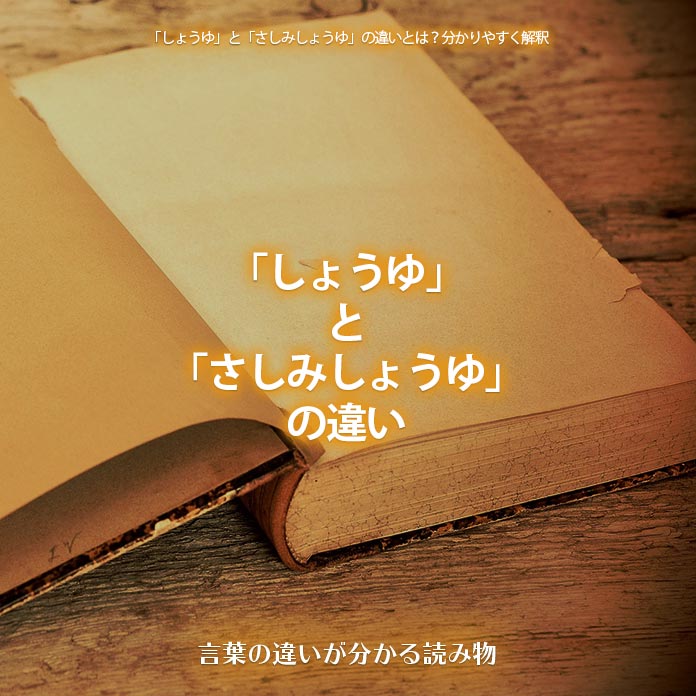
「しょうゆ」と「さしみしょうゆ」の違いを、分かりやすく解説します。
「しょうゆ」は、「日本独特の調味料の一つ。
小麦や大豆を原料とした麹に、食塩水を加えて、発酵させたあとで、絞った液体のこと」という意味があります。
一方で、「さしみしょうゆ」は、「刺身を食べるためのしょうゆ」という意味があります。
「しょうゆ」は濃い口しょうゆ、たまり?油、さらに「さしみしょうゆ」も含む、「しょうゆ全般」を指す言葉になります。
一方で、「さしみしょうゆ」は、刺身を美味しく食べるために作られた「しょうゆ」のみを指すという違いがあります。
まとめ
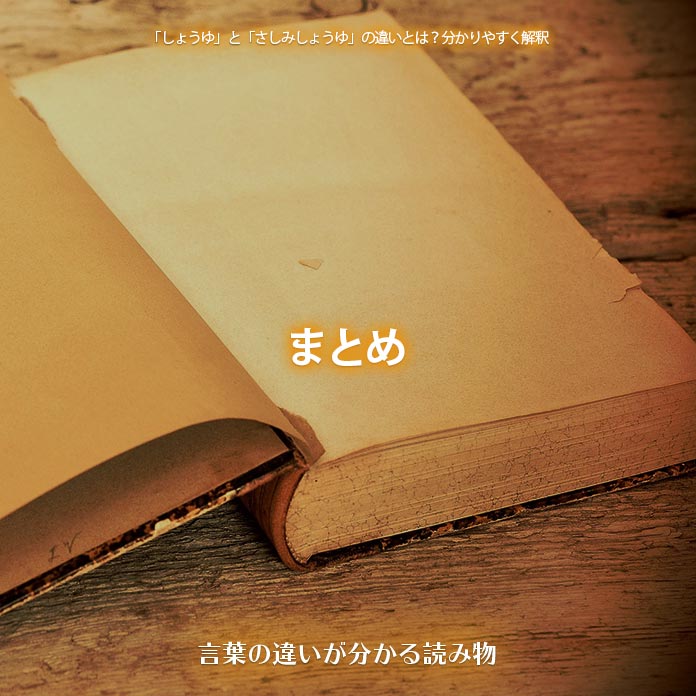
「しょうゆ」と「さしみしょうゆ」の違いについて見てきました。
2つの言葉には明確な意味の違いがありました。
2つの言葉の意味の違いを知ることで、スーパーなどに「しょうゆ」を買いに行った時、きちんと欲しいものをえらべるようになりそうです。